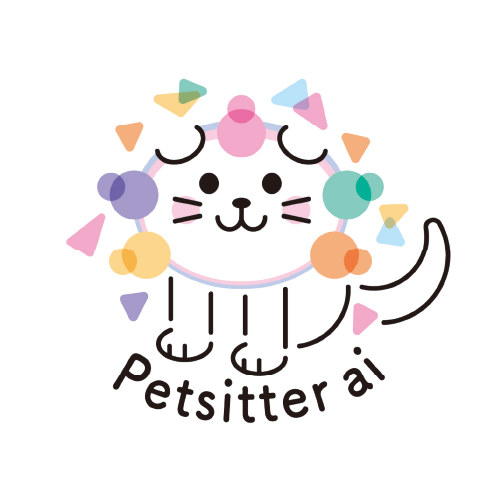こんにちは!さいたま市でペットシッターをしている「ペットシッターあい」です。皆さんの大切なご家族であるワンちゃん、ネコちゃん、そのほか沢山のペットさん達と毎日楽しく過ごさせていただいています。
私は、ペットシッターとしてより専門的な知識を身につけ、皆さんの大切なご家族を深く理解するために、愛玩動物看護士の資格取得を目指しています。
私だけでなく、一緒に働いているスタッフも日々、知識向上のために勉強を重ねています。
学んでいく中で、私たちは皆、動物たちが私たちとは全く違う感覚で世界を捉えていることに、日々驚かされています。このコラムでは、そんな動物たちの不思議な世界を、皆さんと一緒に探求していけたら嬉しいです。
さて、皆さんは「この色って、何色に見える?」と友だちや家族と話していて、意見が分かれた経験はありませんか?
実は、私が以前働いていたペットショップで、スタッフと蛍光色のバインダーの色について「黄色か黄緑か」で意見が分かれたことがありました。
人によって違う色の見え方:科学的な根拠
私はどちらかというと「黄緑色」に見えたのですが、「いやいや、黄色でしょ」と主張するスタッフもいました。結局、半々くらいの意見に分かれ、答えは出ませんでした。(今思えば、こんなささいなことで和気あいあいと談笑していた日々が懐かしいです。)
この出来事から、色って見る人によって違うんだなと改めて実感したことを覚えています。
この違いは、人間の目の構造と脳の働きが深く関係しています。私たちの目の奥にある網膜には、「錐体細胞(すいたいさいぼう)」という光受容細胞があります。錐体細胞は光の波長(色の違い)を識別する役割を担っており、光の三原色である赤、緑、青のそれぞれに反応する3種類が存在します。人間はこの3種類の錐体細胞をバランスよく持っているため、多様な色を認識できます。これを「三色型色覚(さんしょくがたしきかく)」と呼びます。
しかし、この錐体細胞の感度や数は一人ひとり異なるため、光の波長に対する反応にわずかな違いが生じ、色の見え方にも個人差が生まれます。
また、先天的に特定の錐体細胞が働かないことによって起こる色覚異常(色覚特性)も存在します。これは、遺伝子の違いによって色の見え方が異なるという個性の一つです。例えば、赤色を認識する錐体細胞がうまく機能しない場合、赤が他の色(くすんだ緑や茶色など)と区別しにくくなることがあります。このように、私たち人間の間にも、色の見え方には学術的な裏付けのある違いがあるのです。
人間の赤ちゃんと動物の成長:それぞれが持つ特別な能力
私は去年子どもを出産し、これまで動物と関わってきた経験から、忘れられない感動を覚えました。
それは、子どもが産まれた翌日のことです。子どもがもう目をぱっちり開けて外の世界を不思議そうに眺めている姿があり、とても驚きました。まだ視力はほとんどないはずですが、ぼんやりと光を感じているようで、間違いなく外の世界を認識している。その姿に、ただただ感動しました。
なぜこれほど感動したかというと、これまで20年近く犬や猫と接してきたからです。ご存知の方も多いかもしれませんが、生まれたばかりの子犬や子猫は、目が開くまで約2週間かかります。この時期、彼らは外の世界を光も色も認識できません。外界の刺激から目を守るため、まぶたが閉じた状態で生まれてくるのです。
一方で、子犬や子猫は、目が開いていなくても「自力で」お母さんのおっぱいを探し、力強くお乳を吸いにいくことができます。その姿にも、私はとても感動しました。人間の子どもは、お母さんが抱き上げてあげないと授乳できません。
これは、それぞれの種が持つ「生きるための戦略」の違いです。人間は生まれてから社会的な交流や学習を始めるため、視覚や聴覚が早期に発達するようにできています。一方、犬や猫は、目が開くよりも先に、自力で生き抜くための本能的な能力を優先して発達させるようにできているのです。
ペットたちの特別な五感の世界
この不思議な世界は、視覚だけではありません。皆さんの大切な家族である犬や猫は、人間とは全く異なる五感の世界を生きているのです。愛玩動物看護士の勉強の中で、彼らの感覚器の仕組みを学ぶことは、ペットシッターとして動物たちの行動や感情を深く理解するための鍵となります。
1. 視覚:人間とは違う色の世界
皆さんは、犬や猫がどのような色を認識しているかご存知ですか?
人間が3種類の錐体細胞を持つ「三色型色覚」であるのに対し、犬や猫は人間とは異なり、主に2種類の錐体細胞しか持っていません。この状態は「二色型色覚(にしょくがたしきかく)」と呼ばれ、彼らの目には世界が青と黄色を中心に、それらの濃淡やグラデーションで映っていると言われています。そのため、私たちが鮮やかな赤色に見えるおもちゃも、犬や猫にはくすんだ灰色や茶色に見えているかもしれません。
彼らは色の認識能力を補うように、人間にはない特別な能力を持っています。
-
動体視力: 犬や猫は、動いているものをとらえる能力が非常に優れています。これは、獲物を狩るための本能的な能力であり、遠くにあるわずかな動きも見逃しません。犬は人間より10倍〜20倍も速い動きを認識できるといわれています。以前、私が担当したワンちゃんに、赤いボールを投げてもなかなか反応してくれなかったことがありました。しかし、青いボールに変えたところ、目を輝かせて夢中になってくれたんです。猫がレーザーポインターの赤い光に夢中になるのも、光の点が素早く動くからであり、彼らは色の違いではなく「動き」に強く反応しているのです。
-
タペタム(輝板): 彼らの網膜の裏側にある「タペタム」は、わずかな光も増幅して網膜に戻す働きがあり、これにより暗い場所でもはっきりと物を見ることができます。夜間に動物の目が光って見えるのは、このタペタムが光を反射しているためです。この特別な構造のおかげで、猫は夜間の狩りなどで獲物を見つけやすくなっています。
-
瞳孔の形: 犬と猫では瞳孔の形も異なります。犬の瞳孔は丸い形ですが、猫の瞳孔は光の量に応じて縦に細長くなります。これは、より効率的に光を取り込み、暗い場所でも高い視力を保つための適応です。これにより、猫は薄暗い室内でも、家具の配置を完璧に把握し、ぶつかることなく動き回ることができます。
2. 嗅覚:驚くべき「におい」の世界
犬の嗅覚は、人間の数千倍から1億倍も優れていると言われています。彼らの鼻には、人間よりもはるかに多くの嗅細胞が詰まっています。この驚くべき嗅覚は、単ににおいをかぎ分けるだけでなく、感情や状況を読み取るための重要なツールとなります。
犬は、鼻腔の奥にある「鋤鼻器(じょびき)」という特殊な器官で、におい情報の中でも特にフェロモンを識別しています。このフェロモンは、動物たちの間でコミュニケーションをとるための重要な情報源となり、発情期や縄張りの主張などに使われます。人間が興奮したり、不安を感じたりしたときに発するにおいを嗅ぎ分け、私たちの感情を読み取る能力も持っているのです。
ペットシッターが家を訪問する際に、犬が私のにおいをかぐことで「この人は安全だ」と判断し、安心してくれます。このため、私は訪問の際は香水などをつけず、無臭の物か、穏やかな香りのハンドソープを使うように心がけています。
3. 聴覚:人間には聞こえない音
犬や猫は、人間よりもはるかに広い音域を聞き取ることができます。特に、人間には聞こえない超音波を聞き取れる能力は、彼らにとって重要な情報源となります。犬の可聴域は最大で65,000ヘルツ、猫は最大で64,000ヘルツと言われており、人間(最大20,000ヘルツ)をはるかに上回ります。
ペットシッターが訪問した際に、わずかな足音や声で安心してくれるのも、彼らの優れた聴覚のおかげです。彼らは、耳を動かすことで音の方向を正確に特定する能力も持っています。これにより、遠くから聞こえる音の正体もすぐに察知できるのです。
ペットの行動を五感で読み解く
私たちは、ついつい人間と同じ感覚でペットを見てしまいがちですが、彼らの行動の多くは、彼ら独特の五感の世界から生まれています。
-
「なぜうちの子は、床のにおいを延々と嗅いでいるの?」 → 地面に残された他の動物のにおい(尿や肉球のにおい)から、その子の性別や健康状態といった情報を読み取っているためです。
-
「なぜ猫は、何もない空間をじっと見つめているの?」 → 人間には聞こえない微かな物音を聞き取っていたり、目に見えない小さなホコリが光の加減で動いているのを追っていたりする可能性があります。
-
「なぜ猫は、足元でゴロゴロ鳴きながら、ふみふみ(前足で交互に押す仕草)するの?」 → 足の裏にある汗腺から、においの情報(フェロモン)を出し、自分のにおいをつけて安心している行動です。
高齢ペットの目の変化とケア
動物の目の健康は、年齢とともに変化します。高齢になると、目の病気にかかるリスクが高まります。
-
白内障: レンズが白く濁り、視力が低下する病気です。初期はあまり気づかないこともありますが、進行すると目が白っぽく見えるようになります。
-
緑内障: 眼圧が上昇し、視神経を圧迫することで、激しい痛みを伴い、失明につながる可能性のある病気です。
これらの病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。日々の暮らしの中で、目が白く濁っていないか、充血していないか、何かを怖がるようになったり、家具にぶつかったりしないかなど、注意深く観察してあげてください。異変を感じたら、すぐに動物病院に相談しましょう。ペットシッターとして、私はそうした目の変化についても、飼い主さんにお伝えできるよう、日々勉強を重ねています。
ペットシッターとしての実践とサービス
ペットシッターとして、お客様の大切なご家族と向き合うとき、この「五感の違い」や「目の健康」に関する知識は、大きな強みになります。
例えば、私達はお世話をさせていただく際、その子の個性に合わせておもちゃを選んでいます。青や黄色のボールは彼らにとって見つけやすく、遊びへの興味を引きやすいのでおすすめです。また、猫がリラックスできる環境を整えるため、落ち着いた色合いのブランケットを用意するなど、色を意識した工夫もしています。
浦和区を中心に活動するペットシッターとして、私はご自宅へお伺いし、ただお世話をするだけでなく、その子の個性や特性を深く理解することを大切にしています。ご家族様が安心してご旅行やお仕事に行けるよう、細やかな気配りと専門的な知識で、心温まるサービスをご提供します。
さいたま市にお住まいで、ペットのお留守番にお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談くださいね。
まとめ:それぞれの「見える」世界を理解する
私たちの当たり前の「見える」世界は、ペットたちにとっては全く違う世界です。彼らが見ている世界を理解することは、ペットの行動や感情を深く理解することにつながります。
愛玩動物看護士の資格取得を目指し、日々学ぶことは、動物たちが私たちとは違う「見方」や「感じ方」をしていることに感動させられます。
これからも、皆様に信頼されるペットシッターとなれるよう、皆さんの大切なご家族がどんな世界を見ているのか、そしてどんなお世話が一番喜ばれるのかを一緒に考えていけたら嬉しいです。
ペットシッターあい 浦和店
-
営業時間: 9:00 ~ 19:00
-
住所: 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目11-27-105
-
電話番号: 📞 050-1807-9090
-
ウェブサイト: ペットシッターあい 浦和店WEBサイトはコチラ
-
LINE登録: LINE登録はコチラ
-
Instagram: お世話の様子やあいの情報が分かるインスタはコチラ
これからも、皆様と大切なペットたちが、笑顔あふれる毎日を送れるよう、私たち「ペットシッターあい」は尽力してまいります。